クレシタの挑戦 認知科学に基づいたコーチングとは何か(実践編)
このシリーズでは、クレシタそのものや、人事・組織づくり、個性についてなど幅広く社長にインタビューをしていきます。
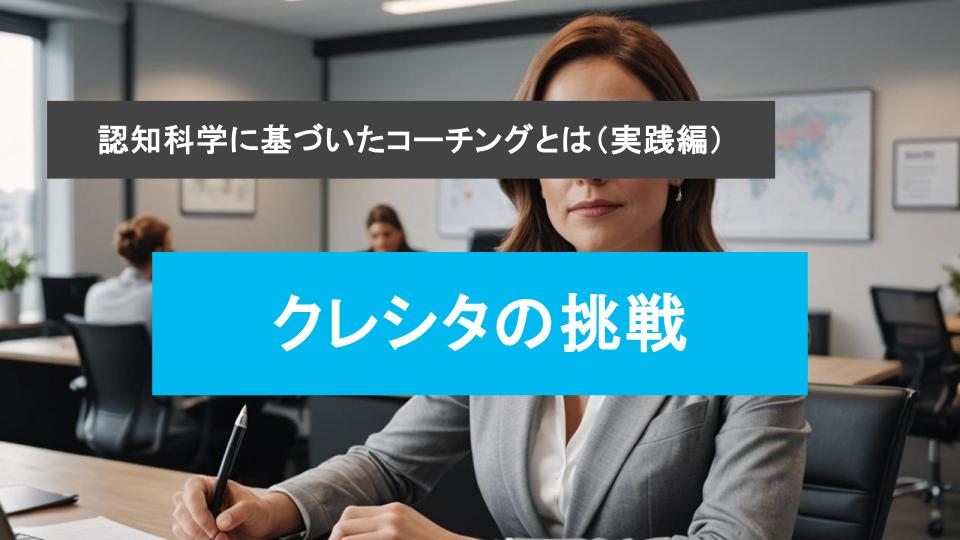
今回は12回目になります。前回のインタビューはこちら

改めて今回は認知科学に基づいたコーチングを用いての自己効力感が高くなりやすい領域の特定方法と向上方法を教えて頂きます。よろしくお願い致します。

よろしくお願いします。

改めて具体的にどんなことをするんでしょうか?

まず大きく二つに分かれています。そもそも自己効力感が一番高まることって何?っていう自己理解的なフェーズと、それに基づいたゴール設定をするフェーズに分かれます。
前半の自己理解についてですがそもそもやれる気って誰かに励まされたり、教えられて身につくものではないというのはなんとなく感覚でわかりますかね?

確かにこうすればやれる気出るよって言われても、ちょっとイメージつきづらい感じはしますね。

ですよね。一番やれる気が高まるってどういう時かっていうと、 自分がめちゃくちゃ自信があることだったり得意なことだったり、なんでこれみんなできないの?って思ってるようなことです。
だから、インタビュワーさんも今マーケの仕事をしてるわけじゃないですか。私だったらこの報酬をいただいても、それ以上の価値が出せるという自信があるからやってるわけですよね。

その通りです。

問題なのが特に会社員の方が自分の得意分野で勝負してないパターンが多いこと。
たまたまこの大学でこの研究室に行って、この会社に受かってたまたま営業職になりましたとか総務になりましたとか、はたまたエンジニアになりましたとかそういうパターンが多くて、自分が一番得意だからこの職に就きましたと胸を張って言える人がめちゃくちゃ少ないんですね。
なので、自己理解なしでは自己効力感は上げられないっていう今の日本の教育システムの問題的なところもあります。

確かに。その人の得意不得意よりも手につきやすかったり、比較的給料が良かったり、それこそ配属ガチャ的に仕事やポジションが決まってしまう日本の根底の問題がそこにあるんですね。

そうです。なので、まずはお一人お一人からいろいろお話をさせていただいて、一緒に何があなたの得意で夢中でやれるものなのかっていうのを見つけていく。
そして、これだけやれる状況を作れたらどうですか?で問いかけたときにほぼ皆さんが「絶対できます!これだけやれるんだったらもうずっと仕事できます」みたいな状態になれるので、自然と自己効力感が高まっていくわけですね。
まずこれが第一フェーズになります。
二つ目がゴール設定。皆さん基本的に生活するために仕事をしている、特に会社員の場合は多いですよね。

そうですね。

または目標はあるけれども、よく聞いてみると上司となんとなく1on1で作ったものだったり、会社から設定された売上やノルマの話だったりします。
でもそんな目標だと「やれる気」なんて起きませんよね。
だから自己理解をもとにしたゴールを設定しなおす。
仮に自分が無意識でやっちゃうのに成果が出てしまうことだけやっている状態だったら、自分はどういうことを成し遂げたいのか、どういう状態でありたいのかということを1on1で膨らませていくイメージですね。
それがゴールに設定された時に人は「これだったら絶対にやりたいです」という気持ちがあふれて「やれる気」が上がっていく。自分の常識というフィルターが外れていって、今までそんなに大した働きをしてこなかった人が生まれ変わったかのようにどんどん仕事をしていくっていう状態が生まれるというからくりです。

なるほど。確かにこのお話を伺うと、そうなれたらどんなにいいかと感じました。
ただ、一方で私含めどうなりたいのかっていうのが具体的にイメージできてない人も結構多いんじゃないかなって思うんですよね。自分の理想像それが本当の入り口だっていうお話だったんですけど、そこを探すのがすごく難しいと思うのですがいかがでしょうか?

そこも弊社でノウハウがあり、ポイントとしては無意識の観察になります。
質問ですが、人間の意識と無意識はだいたい何対何で構成されているっていう話聞いたことありますか?

聞いたことありませんね。

意識が5%で無意識が95%で構成されてるという一つの見解が出てます。

そんなに差があるんですか?

はい。マーケをやっているインタビュワーさんだったら思い至るシーンがあると思いますが、結構人の心理って操れますよね?

そうですね。マーケティングでも誘導みたいなものは行います。

ですよね。文章の中に購買欲をかきたてるような表現を入れちゃったりとか、ステルスマーケティングとかもそうですよね。そういう意図を感じさせなくとも。実は購買行動を書き立てる手法がたくさん確立されてます。
それが可能なのは人間の無意識の方が大きいから、意識じゃコントロールできない領域の方が大きいからなんです。

納得しました。

逆に言うと、自分だけで考えるっていうのは意識の方に集中させることになるので、少なくとも自分の半分以上の領域を無視した行動になります。
なので、弊社では逆に普段見てない無意識の方を観察するメソッドを使って、あなたは実はこういうこと考えてますよね、というお話できるので、一気に自己理解が進むし、自分が本当にやりたいことが見つかっているっていうイメージですね。

すごいですね。
95%の無意識の中から読み取っていくのはメンタリストみたいだなと感じます。
一方で無意識の観察というのはすぐに誰でもできるものなのでしょうか?

そこは誰でもできるということではなくてしっかりと訓練された人しかできません。
もう少し具体的に言うと、「この人今本当にやれる気高まってるな」とか「自信が持ててるな」っていうのを観察できる人じゃないといけなくて。
要は見る人が自分がそういう状態である。っていうのが必須条件になります。

なるほど。確かに導いてもらうにしても、その人自身が理想の状態になってないと自分がどうなっていくのかが、具体的にイメージしづらいと思うので本人がまずそもそも自己効力感が高い状態でないといけないですよね。

そうですね。もう一つは子育てを経験したことがない人がその辛さがわからないのと同じで、「どういう状態が自信があるか」というのを自分の中で理解しておかないと、目の前の顧客が気を使って自信があるように見せてるのかとかそういうのがわからりません。
だから、自分が今自信がある状態であって、今目の前の顧客も今自分と同じような状態になりつつあるって判断できる人ではないと本当の意味で無意識の観察はできません。

とても深いですね。確かに仕事ではプレゼンをするときには自信を持って見せなきゃいけないと思ったり、商談の場では意図的に自信があるように見せることはあると思いますが、コーチングではそれを見破る必要があるということですね。
かなり難しそうに感じるのですが、実際如何でしょうか?

ここに関しては、やはり自分がどれだけ体現しているかがポイントになります。逆に言うと理論だけを勉強した人ができることではないですね。

なるほど。最初に同じものを見たときに得られる情報が違うというお話があったと思いますが、やり方を目で見て、知識として知ったとしてもそれが実行できる、コーチングができるっていうのは別なんですね。
ここまでありがとうございました。
では次回、より具体的な現場におけるコーチングの進め方や効果などを教えて頂ければと思います。


